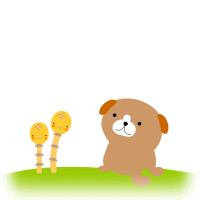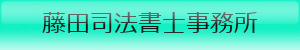債務整理・借金問題無料相談室 藤田司法書士事務所が管理・運営しています。
消滅時効Q&A1
の解決に向けて 無料相談受付中高知県幡多郡四万十市の司法書士事務所です。
債務整理・借金・多重債務・自己破産・過払い請求問題
| 相談の流れ | |
| 相談の流れ | |
| 相談の方針 | |
| 相談事例 | |
| 相談事例 4 | |
| 消滅時効 | |
| 消滅時効の期間計算 | |
| 消滅時効Q&A | |
| 消滅時効解説 | |
| 相続後の過払い請求 | |
| 債務整理Q&A | |
| Q&A 4 | |
| Q&A 5 | |
| Q&A 6 | |
| Q&A 7 | |
| Q&A 8 | |
| Q&A 9 | |
| Q&A 10 | |
| Q&A 11 | |
| Q&A 12 | |
| Q&A 14 | |
| Q&A 15 | |
| Q&A 16 | |
| Q&A 17 | |
| Q&A 18 | |
| Q&A 20 | |
| Q&A 21 | |
| Q&A 22 | |
| Q&A 23 | |
| Q&A 24 | |
| Q&A 25 | |
| Q&A 26 | |
| Q&A 28 | |
| Q&A 29 | |
| 自己破産Q&A | |
| 自己破産Q&A 1 | |
| 自己破産Q&A 2 | |
| 自己破産Q&A 3 | |
| 自己破産Q&A 4 | |
| 自己破産Q&A 5 | |
| 自己破産Q&A 6 | |
| 自己破産Q&A 7 | |
| 自己破産Q&A 8 | |
| 自己破産Q&A 9 | |
| 消滅時効Q&A 1 | |
| 消滅時効Q&A 2 | |
| 消滅時効Q&A 3 | |
| 消滅時効Q&A 4 | |
| 消滅時効Q&A 5 | |
| 消滅時効Q&A 6 | |
| 消滅時効Q&A 7 | |
| 消滅時効Q&A 8 | |
| 消滅時効Q&A 9 | |
| 債務整理 | |
| 任意整理 | |
| 任意整理の流れ | |
| 過払い金返還請求 | |
| 過払い金返還の流れ | |
| 自己破産 | |
| 個人再生手続 | |
| 貸金業法 | |
| 総量規制 | |
| 指定信用情報機関 | |
| 司法書士紹介 | |
| 問い合わせ | |
|
消滅時効Q&A
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。
Q1 私は、借り入れも返済もどちらか遅いときから5年以上前で、 消滅時効は完成していますか?
※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。
以下は、新法により説明しています。
説明で示される条文は民法の条文であり、現行新法の条文です。
A 消滅時効が完成しない事情がなければ、消滅時効が完成している可能性があります。(新法)
「消滅時効の完成しない事情(時効の完成猶予)」とは、ある事実が生じた場合に、その事実の状態が終了するまでは時効が完成しない(完成猶予)という制度です。 例えば、借金をしている人(A)が、債権者(B)から訴訟を提起された場合「時効の完成猶予」となり訴訟手続きが終了するまでの間、原則時効は完成しません。
そして、裁判手続きで「AはBに借金を払え」と言う判決が出て確定した場合、新たに消滅時効が進行を開始する(再びゼロからスタートする)ことになります。(時効の更新 新法)
そして確定判決によって確定した権利については、時効期間は10年となります(第169条)
「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。 具体例: 訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効期間が開始されます(時効の更新) 時効の完成猶予、更新になる場合については、民法147条以下に定められています。
時効の完成猶予
下記の行為がなされた場合に時効が完成しない(完成猶予)ことになります。
消滅時効とは
消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で
定められている制度です
令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。
消滅時効Q&A
消滅時効の更新と完成 (更新=旧法の中断)
く解説します。
それ以降 は借り入れも返済もしていません。
そしてある状態になった時点で新たに消滅時効が進行を開始する(再びゼロからスタートする)ことになります。(時効の更新 新法)
(例:
消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)
1、裁判上の請求(訴訟等)提起した場合
2、支払督促
3、起訴前和解、民事調停法上の調停、家事事件手続き法上の調停
4 破産手続参加、再生手続き参加、更生手続き参加(以上、147条)
5 強制執行・強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売手続
・財産開
示手続(148条)
6 仮差押え、仮処分(149条)
7 催告(150条)(裁判によらない請求)
8 債務の承認(152条)
9 天災等(161条)
10 協議を行う旨の書面による合意(151条)
11 時効の期間の満了前6か月内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代
理人がないとき
未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対
して権利を有するときは、行為能力者となった時又は後任の法定代理人
が就職した時から6カ月を経過するまでの間(158条)
12夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時
から6カ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(159条)
13相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は
破産手続開始の決定があった時から6カ月を経過するまでの間は、時効
は、完成しない(160条)
請求とは裁判上の請求ということになります。
訴訟を提起することが必要です。
訴訟を介さない請求は「催告」となり催告した後の6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しません。(時効の完成猶予 150条)
6か月以内に上記で示した権利が確定した場合に更新となります(新法 147条)
時効の更新
1 確定判決・確定判決と同一の効力を有するものによる権利の確定
(147条2項)
2 強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売手続・財産
開示手続の事由終了時 (148条2項)
3 債務の承認(152条1項)
まとめ
消滅時効が 更新されていなければ、消滅時効が完成している可能性があります。
「消滅時効の 更新」とは、進行している時効の期間が中断され更新されることで、
中断された時効期間はその後、再びゼロからスタートすることになります。
時効の 更新になる場合については、民法147条以下に定められています。
いずれの事例も返済期日は2011年3月31日とします。
消滅時効の起算点と期間の計算の方法については
「消滅時効の起算点と期間計算」をご覧下さい。
事例1
Aさんは2010年5月1日貸金業者Zから20万円を借入(返済期日は、同年3月31日とする)、 2011年6月1日に借入金の一部である10万円を返済しました
(Aさんの消滅時効の起算点は返済期日の3月31日です。
消滅時効の期間の計算は4月1日から開始されます。
6月1日に返済した事実は「債務の承認」となり、「時効の更新」となります。
更新後、再び消滅時効の期間の計算が開始されます
(期間の起算日は民法140条の初日不算入により6月2日になります。)
そのまま何事もなく(返済も借入もせず)、2016年6月1日が経過しました。
(民法143条2項により満了日は6月1となります)
Aさんは2016年6月2日の時点で消滅時効を主張することができます。
事例2
Bさんは2010年2010年5月1日貸金業者Xから20万円を借入(返済期日は、同年3月31日とする)、 2011年6月1日に借入金の一部である10万円を返済しました
しかし、消滅時効が完成する前の時点である2013年5月1日、貸金業者 XからBさんを被告として裁判所に貸金返還請求の訴えが提起されました。
訴訟の結果、Xが勝訴し、2013年7月1日に判決が確定しました。
Bさんは2016年6月2日に消滅時効を主張しましたが、「時効の更新」により、 Bさんの主張は認められませんでした。
ちなみにBさんの消滅時効の完成の時期は、判決の確定した日から10年後の 2023年7月2日となります。
判決が確定した場合の消滅時効の期間については、Q&A2
をご覧下さい。
時効の援用とは
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の
成立を主張すること。
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するもの
ではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が
消滅する。
もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、請求されたり、
訴訟を提起されたりした場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。
消滅時効とは
消滅時効について詳しくは「消滅時効」をご覧ください。
消滅時効詳細
会話形式でわかりやすく解説しています。
このサイトは、藤田司法書士事務所が管理・運営しています。
事務所案内 著作権・免責 リンク集 個人情報保護方針 サイトマップ
藤田司法書士事務所
Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved